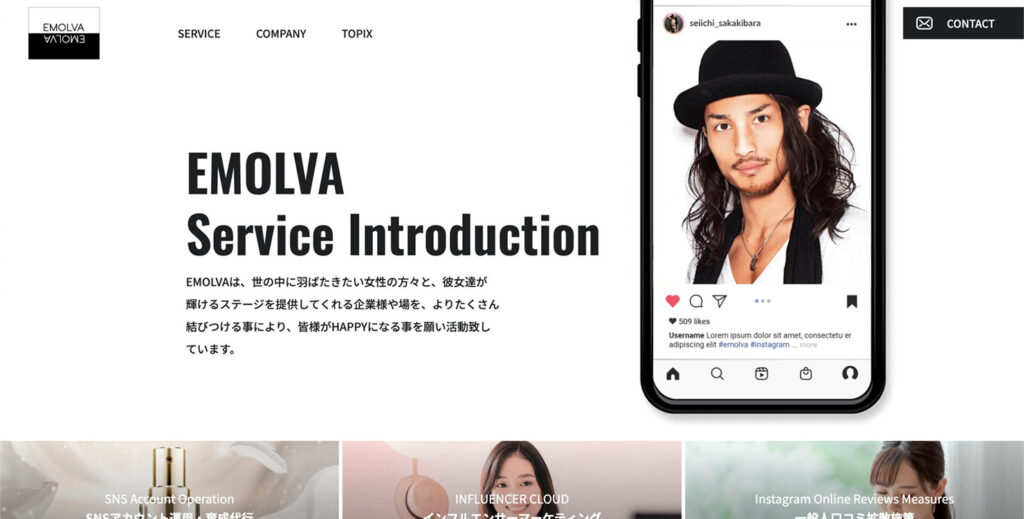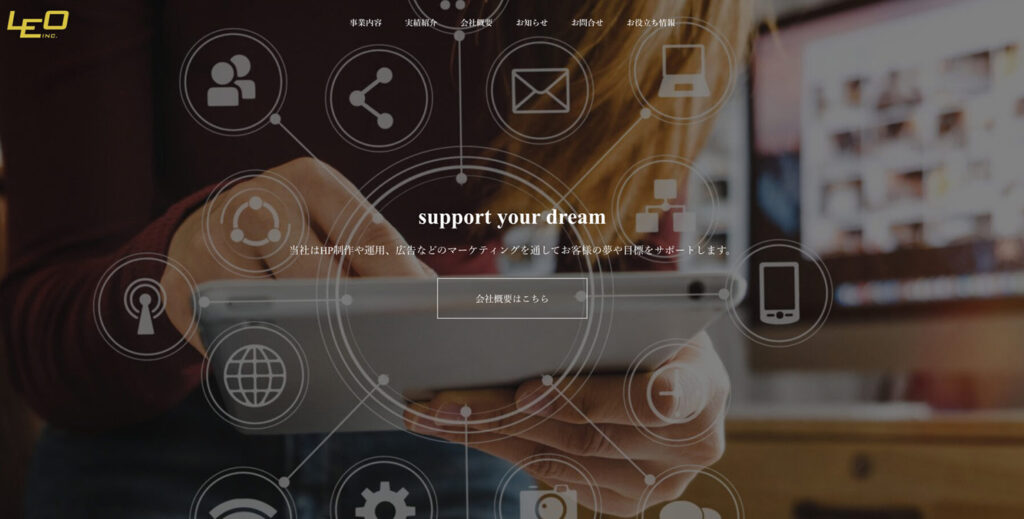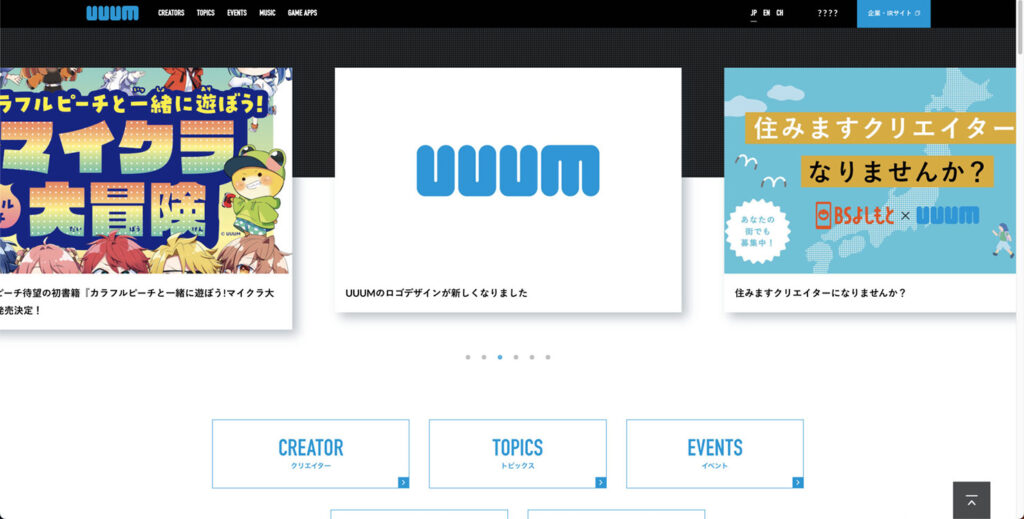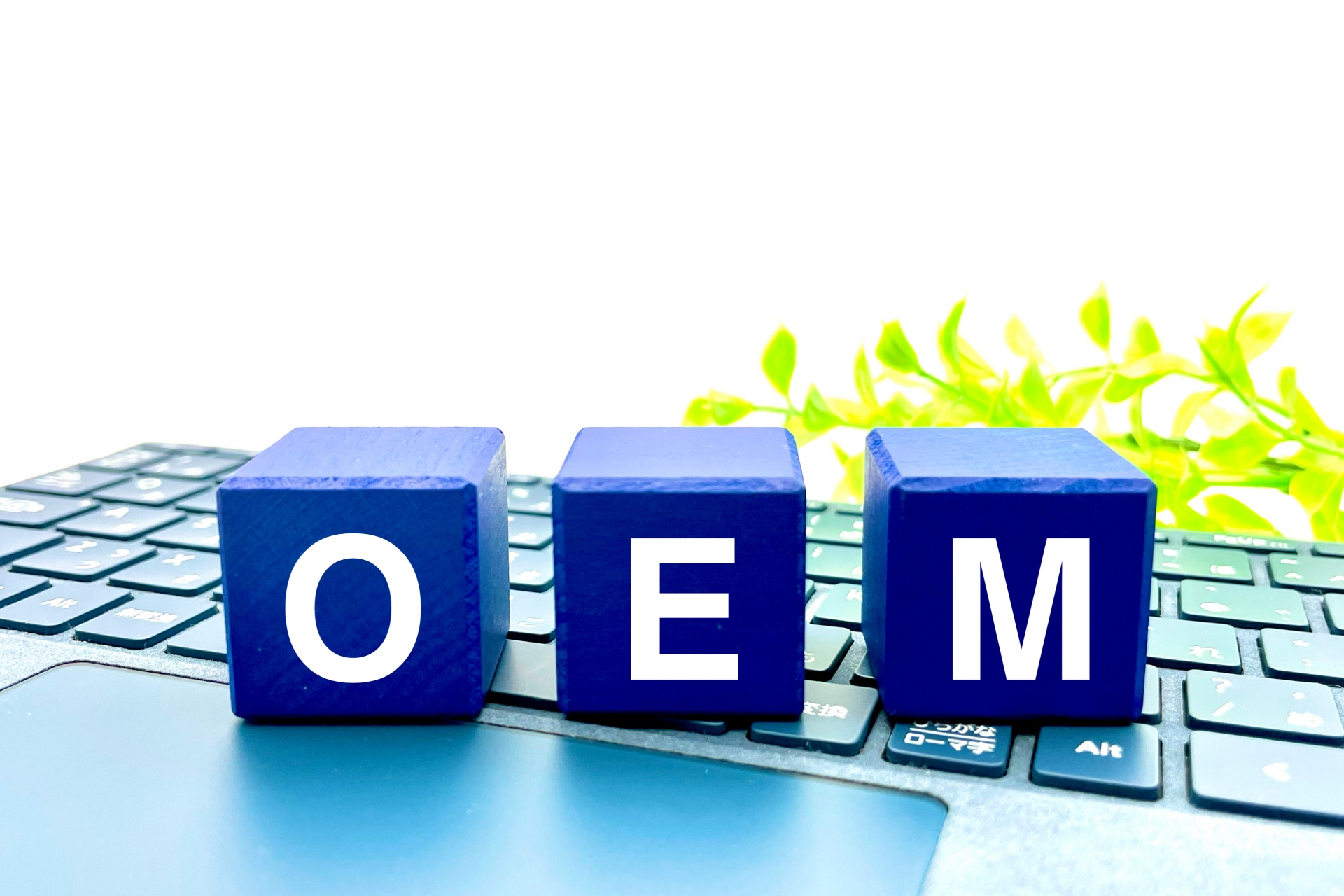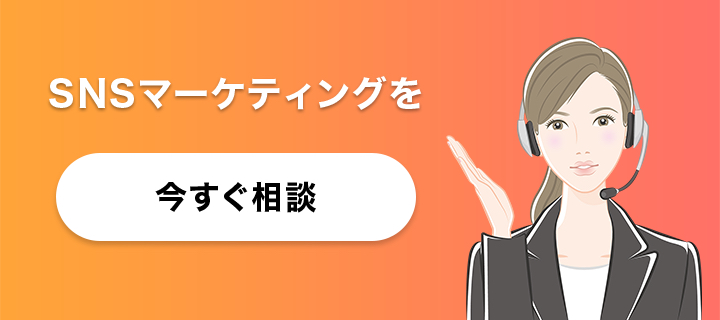インフルエンサーマーケティングの効果測定方法とは?指標(KPI)の選び方まで徹底解説

インフルエンサーマーケティングの効果は多くの事例で立証されています。
その反面、効果測定の難しさが担当者の大きな負担になっているのも事実です。
そこでこの記事では、インフルエンサーマーケティングの効果測定が難しい理由を明らかにしたうえで、数値化できる効果の検証方法を解説していきます。
目的やSNSごとに適したKPIの選び方も解説していますので、ぜひ今後のインフルエンサーマーケティングにお役立てください。
目次
インフルエンサーマーケティングの効果測定が難しい理由とは?
結論から言うと、インフルエンサーマーケティングの効果測定は不確実性が高いため、簡単ではありません。
インフルエンサーマーケティングの効果測定を難しくしている要因として、以下の4点が挙げられます。
- 売上との直接的な因果関係が見えにくい
- 定量指標だけでは効果が把握できない
- SNSごとにユーザー行動や計測精度が異なる
- 施策目的に適したKPIを設定しないと効果が見えづらくなる
順番に解説していきます。
売上との直接的な因果関係が見えにくい
インフルエンサーマーケティングの効果測定を難しくしている最大の要因は、売上との直接的な因果関係が見えにくいからです。
インフルエンサーの投稿を見て興味を持ったとしても、即買いする人はそう多くはありません。
むしろ、たまたまお店で見かけた時に「そういえば、おすすめされていたな!」と思い出して、後日購入する人の方が多いのです。
ライブ配信中に購入したなら別ですが、後日購入した場合は因果関係を証明することはできません。
定量指標だけでは効果が把握できない
成果を数値化できる定量指標だけでは、正しい効果は把握できません。
インフルエンサーマーケティングは、ブランド認知度の向上や見込み客の育成など、幅広い目的で多用されています。
なかには数値化できない効果もあるため、定量指標だけで成否を判断することはできません。
SNSごとにユーザー行動や計測精度が異なる
SNSごとにユーザー行動や計測精度が異なるのも、インフルエンサーマーケティングの効果測定を難しくさせている大きな理由です。
なかには直接的なCVを促すリンクを設定しづらいSNSもあり、流入経路の測定さえままなりません。
施策目的に適したKPIを設定しないと効果が見えづらくなる
KPIは、施策目的にあわせて設定するのがセオリーです。
ブランド認知の向上が目的なのに購買数をKPIに設定していては、インフルエンサーマーケティングが本来の目的に貢献した成果を正しく測定することはできません。
インフルエンサーマーケティングの効果指標(KPI)の種類
設定したKIPがどのくらい達成したかで、インフルエンサーマーケティングの定量的な効果を測定することができます。
ただし、設定すべきKPIはインフルエンサーマーケティングを実施する目的によって異なるため、注意が必要です。
たとえば、目的に適したKPIが「クリック数」だった場合、「いいね!数の増加」=「効果測定の結果が良好」と評価することはできません。
そこでこの章では、インフルエンサーマーケティングを実施する代表的な以下5つの目的にあわせて、最適な効果指標(KPI)をご紹介していきます。
- 認知拡大の指標には「リーチ数」や「インプレッション数」
- 興味関心を測るには「エンゲージメント数」
- 購買意欲を測るには「クリック数」や「リンク遷移数」
- 販売促進の成果には「クーポン利用率」や「購入数」
- 中長期の成果は「リピート率」や「LTV」
順番に解説していきます。
認知拡大の指標には「インプレッション数」や「リーチ数」
インフルエンサーマーケティングを実施する目的が「認知拡大」だった場合、設定すべきなのは「コンテンツをどれだけ多くの人に見て貰えたか」を表すKPIです。
これをSNSならではのKPIに置き換えると、以下のようになります。
▼認知拡大を目的としたインフルエンサーマーケティングに適したKPI
- インプレッション数:投稿が表示された回数
- リーチ数:投稿を見たユーザー数(ユニークユーザー数)
- 動画再生数:動画が再生された回数
- 投稿の滞在時間:投稿を閲覧している時間
- シェア数:コンテンツが共有された数
上記のKPIを設定して効果を最大化するには、知名度が高くフォロワー数が多いインフルエンサーをキャスティングするのがおすすめです。
リーチ力が高いインフルエンサーを起用することで、ブランドや商品の存在をより多くのSNSユーザーに認知して貰えます。
興味関心を測るには「エンゲージメント数」
ユーザーの「興味関心」を引き出す目的でインフルエンサーマーケティングを実施する場合、設定すべきなのは「ユーザーがポジティブな反応を示した程度」、つまりエンゲージメントに関連するKPIです。
具体的には、以下のようなKPIが適しています。
▼興味関心を目的としたインフルエンサーマーケティングに適したKPI
- 動画視聴完了数:動画を最後まで見てくれた人の数
- 動画視聴率:視聴者数に対する視聴完了者の割合
- いいね数:「いいね!」がタップされた数
- いいね率:投稿が表示された回数などに対して、「いいね!」された割合
- シェア数:コンテンツが共有された数
- シェア率:投稿が表示された回数などに対して、シェアされた割合
- コメント数:獲得したコメントの数
- コメントの質:興味を持ってくれた人からのコメント
- URLクリック数:HPやLPへのURLリンクが、クリックされた回数
- URLクリック率:視聴者数に対してURLリンクがクリックされた割合
- UGC数:ユーザーが自作したブランドや商品に関連する投稿
- 自社アカウントフォロワー数:自社アカウントのフォロワーが増えた数
これらのKPIを設定したインフルエンサーマーケティングで成果を伸ばすには、ハッシュタグチャレンジなどのキャンペーンと組み合わせるのがおすすめです。
とくにユーザー参加型のキャンペーンはSNSでの拡散スピードが速く、絶大な影響力を発揮します。
より多くのSNSユーザーに興味・関心を持ってもらえるうえ、非ターゲット層にも情報が伝わりやすいため、ブランド認知度の向上にもつながります。
購買意欲を測るには「クリック数」や「リンク遷移数」
インフルエンサーマーケティングを実施する目的が「購買意欲の向上」だった場合、設定すべきなのは「見込み顧客の増加」を表すKPIです。
たとえば、以下のようなKPIが適しています。
▼購買意欲の向上を目的としたインフルエンサーマーケティングに適したKPI
- URLクリック数:HPやLPへのURLリンクがクリックされた回数
- URLクリック率:視聴者数に対して、URLリンクがクリックされた割合
- SNS経由のサイト滞在時間:SNSからサイトへ流入し、閲覧している時間
- SNS経由のサイト回遊回数:SNSからサイトへ流入した人の回遊数
- コメントやDMの数:商品などに対して寄せられた、質問や意見の数
- コメントやDMの質:購買熱量高いコメントの獲得
- レビューの獲得数:商品などに対し、顧客から寄せられた感想や評価の数
- ユーザー登録数:新規会員登録、メルマガ登録など
- 投稿保存数:後から見返したいと思って貰えた数
上記のKPIを設定して効果をあげるには、レビュー投稿で高評価を得ているインフルエンサーを起用するのがおすすめです。
なかでも、特定ジャンルの有資格者や専門家としてプロ視点の情報を発信しているKOLのレビューには、フォロワーの購買意欲を後押しする力があります。
販売促進の成果には「クーポン利用率」や「購入数」
インフルエンサーマーケティングを実施する目的が「販売促進」だった場合、設定すべきなのは「購入」を表すKPIです。
具体的には、以下のようなKPIが適しています。
▼販売促進を目的としたインフルエンサーマーケティングに適したKPI
- SNS経由サイト遷移数:URL経由でHPに流入したユーザー数
- ユーザー登録数:クレジットカード情報登録など、顧客情報の獲得数
- クーポン利用率:配布したクーポンに対し、利用された回数
- 購入数:製品・サービスが購入された数
- 売上、利益:購入に伴う売上と利益額
販売促進に適したKPIを設定した場合、エンゲージメント率が高い「マイクロインフルエンサー」の起用がおすすめです。
中長期の成果は「リピート率」や「LTV」
インフルエンサーマーケティングを実施する目的が「中長期の成果」だった場合、設定すべきなのは「中・長期間にわたって得られる利益」を表すKPIです。
これをSNSならではのKPIに置き換えると、以下のようになります。
▼中長期の成果を目的としたインフルエンサーマーケティングに適したKPI
- リピート率:繰り替えし利用した割合
- LTV:顧客生涯価値(Life Time Value)
LTV(顧客生涯価値)とは、顧客が自社の商品やサービスを利用し始めてから終了するまでの期間に、その顧客から自社がどの程度の利益を得られるかを表す指標を指します。
リピート率やLTVをKPIとして設定した場合、アンバサダーの任命がおすすめです。
商品の愛用者が企業やブランドの「宣伝大使」としてPR活動を行うことで、本当に良い物をおすすめしていると消費者に認知して貰えます。
【SNS別】インフルエンサーマーケティングで重視すべき主なKPIと測定ポイント
インフルエンサーマーケティングの効果測定は、あらかじめ設定しておいたKPIを指標とし、どのくらい達成できたかで評価します。
ただし、SNSごとに測定できるKPIの種類が異なっているため、注意が必要です、
つまり、インフルエンサーマーケティングの効果測定を行う際は、実施したSNSで効果測定が可能なKPIを設定しなければなりません。
そこでこの章では以下4つのSNSをピックアップし、インフルエンサーマーケティングの効果測定方法をKPIの選び方について解説していきます。
- Instagramは「エンゲージメント率」や「保存数」
- X(旧Twitter)は「リツイート数」や「クリック率」
- TikTokは「再生回数」と「視聴維持率」
- YouTubeは「平均視聴時間」と「リンク経由の遷移数」
順番に解説していきます。
Instagramは「エンゲージメント率」や「保存数」
Instagramでインフルエンサーマーケティングを実施した場合は、「Instagramインサイト」で効果測定を行えます。
以下は、Instagramインサイトで効果測定が可能なKPIの一例です。
- インプレッション数(投稿が表示された回数)
- リーチ数(ユニークユーザーの数)
- リール動画の再生回数
- フォロワー数の増加
- エンゲージメント数(いいね!・保存・コメントなど、ユーザーのアクション数)
- ハッシュタグ投稿数の変化
- プロフィールビュー(プロフィールの閲覧数)
- Webサイトクリック数(プロフィールに記載したサイトURLがクリックされた回数)
- メールアドレスクリック数(プロフィールに記載したメールアドレスがクリックされた回数)
なかでも、「エンゲージメント率」や「フォロワー数の増減」を中心に効果測定すると、成果をより明確に把握することができます。
なお、Instagram上でインフルエンサーマーケティングを展開する際は、以下の記事も参考にしてください。
X(旧Twitter)は「リツイート数」や「クリック率」
X(旧Twitter)でインフルエンサーマーケティングを実施した場合は、「アナリティクス」で効果測定を行うのが一般的です、
X(旧Twitter)では以下のような項目を確認することができますが、大半の企業はポスト(ツイート)に関連するKPIを設定して効果測定を行っています。
- インプレッション数(投稿が表示された回数)
- リーチ数(ユニークユーザーの数)
- リール動画の再生回数
- フォロワー数の増加
- エンゲージメント数(いいね!・保存・コメントなど、ユーザーのアクション数)
- ハッシュタグ投稿数の変化
- プロフィールビュー(プロフィールの閲覧数)
- Webサイトクリック数(プロフィールに記載したサイトURLがクリックされた回数)
- メールアドレスクリック数(プロフィールに記載したメールアドレスがクリックされた回数)
なかでも、「エンゲージメント率」や「フォロワー数の増減」を中心に効果測定すると、成果をより明確に把握することができます。
TikTokは「再生回数」と「視聴維持率」
TikTokでインフルエンサーマーケティングを実施した場合は、「インサイト機能」で効果測定を行えます。
以下は、TikTokのインサイト機能で効果測定が可能なKPIの一例です。
- リーチ数
- 動画の再生回数(曜日別、時間帯別の再生回数)
- 平均視聴時間
- プロフィールの表示回数
- フォロワーの増減(男女比や地域などの属性も可)
- いいね!数
- シェア数
- 保存数
TikTokでは「いいね+コメント+シェア率」をもっとも重視しているため、この点を踏まえてKPIを設定しましょう。
なお、TikTokの分析方法については以下の記事で詳しく解説しております。
YouTubeは「平均視聴時間」と「リンク経由の遷移数」
YouTubeでインフルエンサーマーケティングを実施した場合は、「チャンネルアナリティクス」で効果測定を行えます。
以下は、YouTube の「チャンネルアナリティクス」で効果測定が可能なKPIの一例です。
- インプレッション数(動画のサムネイルがユーザーの画面に表示された数)
- インプレッションのクリック率(動画再生回数÷インプレッション×100)
- ユニーク視聴者数
- 動画再生回数
- 平均視聴時間
- 高評価数
- コメント数
- クリック率
- チャンネル登録者数
YouTubeにおけるインフルエンサーマーケティングの効果測定では、多くの企業が「再生回数」や「平均視聴時間」をKPIに設定しています。
インフルエンサーマーケティングの効果測定において注意すべき点とは?
インフルエンサーマーケティングの効果測定を行う際は、以下の注意点に留意する必要があります。
- 目的と指標が一致していないと効果が正しく測れない
- 表面的な数値にとらわれすぎると本質を見失ってしまう
- 短期的な結果に偏ると中長期効果を見落とす可能性がある
- SNSごとの特性を無視すると比較が正しくできなくなってしまう
- データだけに頼るとユーザーの“声”を拾えなくなってしまう
順番に解説していきます。
目的と指標が一致していないと効果が正しく測れない
インフルエンサーマーケティングの効果測定で正しい「答え」を出すには、「目的」と「指標(KPI)」を一致させる必要があります。
たとえば、目的が認知拡大の場合は「視聴」に関するKPIを設定すべきであり、LTV(顧客生涯価値)をKPIに設定しても意味がないのです。
表面的な数値にとらわれすぎると本質を見失ってしまう
インフルエンサーマーケティングの本質(役割)として、以下の3点があげられます。
- 利用者が自分の言葉で商品の魅力を発信し、消費者の理解を促進する
- エンゲージメントを獲得して、認知度を拡大する
- 次に選ばれる確率を上げる
つまり、インフルエンサーマーケティングは「即買い」の訴求ではなく、「次に買うならコレ!」と思って貰えるように、印象づけることなのです。
表面的な売上という数値に捕らわれすぎると、この本質を見失ってしまいます。
短期的な結果に偏ると中長期効果を見落とす可能性がある
たしかに、投稿がバズって短期間で大きな成果をあげた事例はいくつも報告されています。
だからと言って。中長期的な効果を侮るのはおすすめできません。
なぜなら、インフルエンサーマーケティングの効果は、裾野が広がるように波状的に広がり、その影響力は長期的に継続するからです。
SNSごとの特性を無視すると比較が正しくできなくなってしまう
前述した通り、効果測定が可能なKPIはSNSごとに異なります。
とくに、複数のSNSで同時にインフルエンサーマーケティングを展開する場合は、効果測定の結果を正しく比較できるよう、対象のSNSすべてに設定できる共通のKPIを選びましょう。
データだけに頼るとユーザーの“声”を拾えなくなってしまう
インフルエンサーマーケティングの失敗要因として代表なのが、数値で表せる定量データにフォーカスし過ぎて、ユーザーの声に無頓着になってしまうケースです。
極端に言えば、動画の再生回数が100回だったとしても、目的に即した登録チャンネル数が50人であれば、そのインフルエンサーマーケティングは成功しています。
むしろ、見てくれた少数の視聴者の大半がチャンネル登録してくれたのなら、大成功と言えます。
インフルエンサーマーケティングの効果測定を次の成果につなげる方法
この章では、インフルエンサーマーケティングの効果測定を次の成果につなげる、以下4つの方法について解説していきます。
- パラメータ付きURLを使って流入とCVを追跡する
- 限定クーポンコードで購買行動を特定する
- 保存数やプロフィール遷移率から関心度を測る
- アンケートやDMで定性的な反応を拾う
順番に解説していきます。
パラメータ付きURLを使って流入とCVを追跡する
パラメータ付きURLを活用すれば、流入とCVを追跡することが可能です。
たとえば、インスタグラムではストーリー限定で遷移用のURLを貼り付けることができます。
この遷移用のURLにGoogleアナリティスから発行したパラーメータを付けておくだけで、
インスタグラムから商品購入ページへの遷移数や購買数を測定できるのです。
どこから流入してどのくらい購入したのかが分かれば「的」が絞れるため、マーケティングの効率があがります。
限定クーポンコードで購買行動を特定する
限定クーポンコードを活用すれば、消費者の購買行動を特定することができます。
原理は前述したパラメータ付きURLと同じで、たとえばインスタの投稿文にクーポンコードを記載しておけば、遷移先でのクーポンコードの利用率を元に以下の3点が明らかになります。
- インスタグラム経由の購買数
- 購買数は通常時とどのくらい違うのか
- 同時に売れた商品
これらの測定結果を活用すれば、今後のインフルエンサーマーケティングでより効果的な戦略が立てられます。
保存数やプロフィール遷移率から関心度を測る
ユーザーのアクションから関心度を測るのも、インフルエンサーマーケティングの効果測定を次の成果に繋げる代表的なテクニックです。
たとえば、保存数やブックマーク数には、「後で買いたい」「時間がある時にゆっくり見たい」、というユーザーの心理が隠れています。
プロフィール遷移率には、「どんな会社が販売しているのか知りたい」という意図が伺えます。
このように、効果測定によって保存数やプロフィール遷移率などを正確に把握できれば、表面化していないユーザーの関心度を測ることができるのです。
アンケートやDMで定性的な反応を拾う
アンケートやDMを精査すれば、消費者の反応を測定することが可能です。
商品の存在を認知したのがインフルエンサーマーケティングを実施したSNSであれば、施策で得られた効果を数値化することができます、
結果次第で、現状のインフルエンサーマーケティングを継続するか、もしくは別の施策に切り替えるのか、正しい判断が下せます。
まとめ:効果測定を正しく行い、インフルエンサーマーケティングの成果を最大化しよう
この記事では、インフルエンサーマーケティングの効果測定とKPIの選び方について解説してきました。
インフルエンサーマーケティングの効果を、数値化できる定量指数だけで表すことはできません。
なぜなら、商品の存在を認知してもらう、あるいはブランドイメージを浸透させるなど、インフルエンサーマーケティングは幅広い目的に対応しているからです。
この点を踏まえて、フォロワー数の増加率やコメント数といった数値化できる効果を測定し、今後のインフルエンサーマーケティングに役立てましょう。
おすすめの代理店
ディレクション型
マッチング型
事務所型